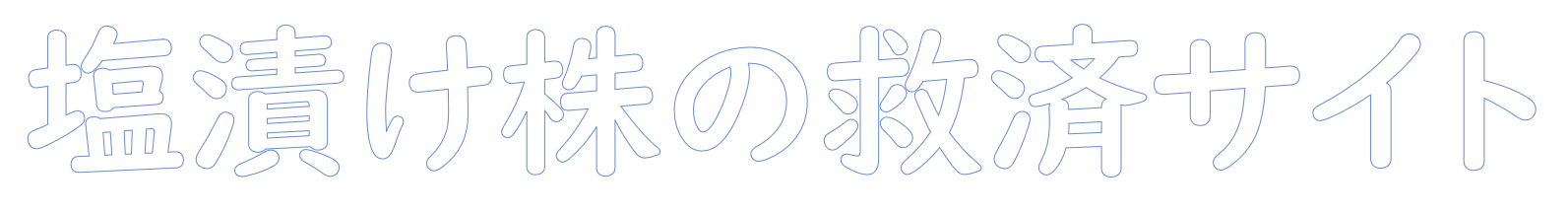手法を正しく理解するために!
この記事のタイトル(ローソク足の読み方)を見て「何をいまさら」と思われたかもしれませんが、ここでは敢えてローソク足の基本的な読み方についての解説を致します。
![]()
ではなぜローソク足による攻略手法ではなく、その読み方なのかと言うと、株取引においてはどんな手法であれ、基本が理解できていなければその意味を大きく読み違えてしまう可能性があるからです。
同じ手法なのにエントリーポイントや利益確定ポイントを読み違えてしまえば、利益を得るどころか損失を出してしまう可能性だってあります。
それなのに負けてしまった場合には「この手法は信憑性がない」とか、「この手法は古くて今の時代には合わない」など、利益を出せないのは全て手法のせいにしてしまい、自身の基礎知識を見直さな人が多いのです。
はっきり言ってプロのトレーダーたちは基本に忠実です。決して基本を蔑ろにすることはありません。ですのでみなさんもこの記事を読んでいま一度ご自身の認識が合っているのかを確かめていただき、そのような過ちを犯さないようにしていただければと思います。
ローソク足の基本
まずは図1をご参照ください。
ちなみに陰線と陽線の色につきましては証券会社によってまちまちですので、このサイトでは後にご紹介するWebチャートに合わせ、陰線を青、陽線を赤で統一させていただきます。
○関連記事
No.005 手軽で便利なWebチャート
ローソク足の解説図

これは基本中の基本なのでみなさんはすでにご存知だと思いますが、ローソク足は1日の取引における4つのポイント(始値・終値・安値・高値)を1本で表した指標であり、ヒゲの長さと胴体の長さの組み合わせから、その日の相場の状況を読み解くことができます。
例えばローソク足の胴体が長ければ相場の勢いが強かったことを意味しますし、ヒゲが長ければ戻す力が強く働いていたことを意味します。また胴体とヒゲが短い場合には売りと買いの力が拮抗していたことを表していますので、次の展開に対して投資家達が様子を伺っている状態であることが分かります。
つまりローソク足は、常に何かしらのサインを出しているのです。ですのでみなさんも、このサインを見逃さないようにして下さい。
下落のサイン
下落のサイン

【図2の解説】
①一時は大きく上昇したものの、売りの力が強く、最終的には下落してしまったため、次の展開も下げとなる可能性が高い。
②最初から最後まで強い売りの力が続いたため、次の展開も下げとなる可能性が高い。
上昇のサイン
上昇のサイン

【図3の解説】
①一時は大きく下落したものの、買いの力が強く、最終的には上昇したため、次の展開も上げとなる可能性が高い。
②最初から最後まで強い買いの力が続いたため、次の展開も上げとなる可能性が高い。
拮抗のサイン
拮抗のサイン

【図4の解説】
①やや売りの方が優勢となったが、ほとんど売りと買いの力が拮抗しているため、次の展開が読みにくい。
②やや買いの方が優勢となったが、ほとんど売りと買いの力が拮抗しているため、次の展開が読みにくい。
この拮抗のサインに関しては、出来高により今後の展開に違いが出てきます。
もし出来高が低ければそれは様子見のサインですので、暫くその状態が続く可能性が高いのですが、もし出来高が高いようでしたら、次は下落か上昇に大きく傾く可能性がありますので、注意が必要です。
この様にローソク足は単体だけでも重要な指標となるのですが、実は繋がった流れを読むことにこそ、その真価が隠されているのです。
ローソク足の真価
みなさんもご存知の通り、ローソク足にはいくつかの種類が存在します。
大きく分けると「分足」、「日足」、「週足」、「月足」の全部で4種類あり、自身のトレードスタイルに合わせて使い分けをするのが一般的ですが、実はこの時、複数のローソク足を参照することが最も重要なのです。
例えばデイトレードなら「分足」を使って分析を行いますが、その時主軸にするのが「5分足」だったとすると、「15分足」と「60分足」の状況を確認することによって、大きな流れの中にある現在の状況を俯瞰的に知ることができるのです。
これはスイングトレードでも同じで、通常なら「日足」を使って分析を行いますが、「週足」と「月足」を確認すれば、「今日は一時的に下げるかもしれないが、数日中には上がってくるだろう」などと言った流れを読むことができます。
もちろん流れを読むためにはそれなりの訓練が必要ですし、テクニカル分析としてもローソク足の情報だけでは精度が落ちますので、他の指標と合わせることによってその真価を発揮することができるのです。
![]()
ちなみにローソク足はテクニカル分析における三種の神器の一つであり、残りの神器は「移動平均線」と「出来高」になりますので、この組み合わせで使用することをお勧めいたします。
また「移動平均線」については次の記事で解説をしていますので、そちらもよろしければご参照ください。
○関連記事
No.004 移動平均線の読み方